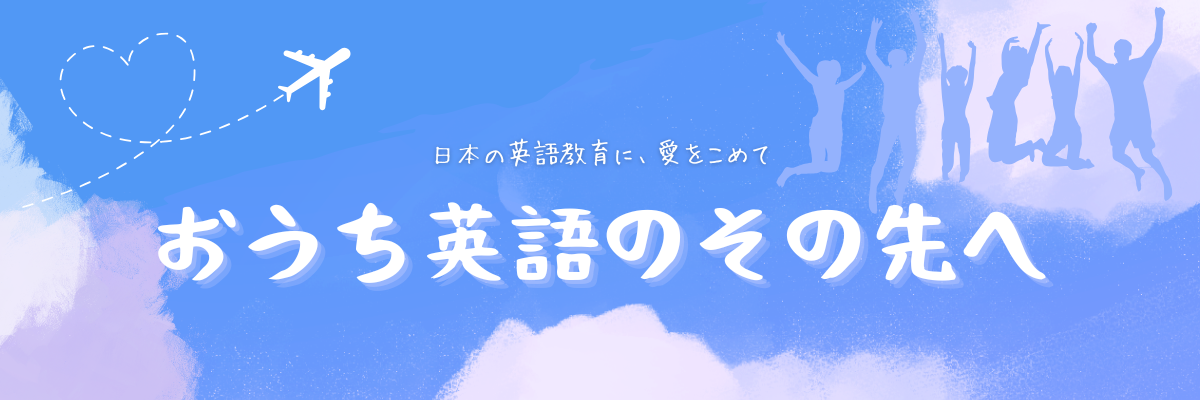こんにちは。桐谷です。
学校での英語の授業、英会話教室、オンラインレッスン…。
子どもたちは間違いなく、以前より多くの「英語に触れる時間」を持つようになりました。
英語教材もバラエティ豊かで、お金をかけなくても英語に触れる機会は日常に溢れています。
それでも、時間の経過と共に、こんな疑問を感じはじめる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「学校でも習い事でも、英語の授業を聞いてるばかりじゃない?」
「インプットはしているけど、話す機会がないよね?」
「今のやり方って、本当に英語力につながっているの?」
我が家でおうち英語を初めて数年、私も同じような疑問を感じていました。
そしてその疑問が引き金となり、海外に飛び出した経験があります。
つまり、そう言った疑問を持つことが、「おうち英語のその先」を考えるうえで、何より大切な一歩になっていくと思うのです。
子どもたちが英語を「受け身」で学びすぎている現実
日本の学校教育、さらには一部の英語教室においても、
「英語に触れさせること」に重きが置かれすぎて、
子ども自身が英語を使う経験が圧倒的に不足しているケースが多々あります。
もちろん、熱意ある先生方は、日々一生懸命、子供たちにアウトプットを促していらっしゃると思いますが、
- 生徒は聞くだけ(ほとんど先生が話している)
- 教材の音声を再生し、ただ聞き流すだけ
- フレーズの暗記だけで「話せるようになった気分」になる
こうした学びを続けていたら、英語が自分の言葉として育てることができないと思うのです。
なぜ「聞くだけ」では話せるようにならないのか?
以前私もお世話になったことがある某英会話教材出版会社ですが、そこから販売されていた看板通信講座の1つ『1000時間ヒアリングマラソン』が、2022年で販売終了となりました。
1000時間ヒアリング達成をしたその後の効果等は分かりませんが、一般的には、言語習得には以下の3つのステップが必要と言われています。
- インプット(聞く・読む)
- 内的処理(理解し、考える)
- アウトプット(話す・書く)
この中で、最も自分の言葉として英語を使えるようになるためには、
アウトプット(=自分で使ってみる)経験が必要不可欠となります。
ですので受け身学習では、3番目のプロセスが育ちません。
そして、日本という島国(=海外から見るとちょっと特殊なほぼ日本人だけの環境)では、この「アウトプット」の機会を自動的に得ることはとても難しく、多くの日本の子供たち、もちろん私たち大人も、「アウトプット」の経験が他国に比べて著しく少なくなってしまうのです。
日常生活で、英語を使う必要が無いからです。
その結果が、「英語をたくさん聞いてきたのに、話せない」という現象です。
つまり「聞けるのに話せない…」と感じるのは、保護者の方やお子さんの努力が足りないわけではなく、ただ、「使ってみる」という最後のステップとそれを実践する機会が足りていなかっただけなのです。
「家庭内」だからこそできる、受け身を越えるアプローチ
自分の家は、評価も成績もない、子どもにとって最も安心できる場所。
だからこそ、家庭内での英語は「聞くだけ」で終わらせない学びに変えられるはずです。
ここで、親子でできる「アウトプット実践法」をいくつかご紹介します。
1. 聞いて終わりを、「話して終わる」に変える
英語のインプットをアウトプットへとつなげるには、「見た・聞いたことを言葉にしてみる」という経験がとても効果的です。
とくに、親子の何気ない会話の中でそれを習慣化することで、子どもは「英語を話すこと」への抵抗を自然と解放していきます。
たとえば、一緒に動画を見たあとにお子さんに、こんな風に尋ねてみてはいかがでしょうか。
“What was your favorite part?”
(どこが一番おもしろかった?)
“What happened in the story?/Can you tell me what happened?”
(何が起きたの?)
“What was funny?”
(何が面白かった?)
“Did anything surprise you?”
(びっくりしたところ、あった?)
日本語でもそうであるように、英語で答えることにも正解はありません。
大切なのは、「自分の言葉で伝えようとする」ことにチャレンジすること。
その一言が、インプットを「使える英語」へと変えていく第一歩になります
聞いたことを、一言でも英語で言ってみるだけで、脳が「理解→再構築→発話」へと動きはじめるのです。
2. 会話の「キャッチボール」を意識してみる
親が一方的に教えるのではなく、お互いに会話のキャッチボールをしながら、言葉を選び、返す。
そんなやりとりが、言語の土台を育てます。
たとえば、こんな何気ない日常での会話はいかがでしょうか。
“Do you want juice or milk?”
“Juice.”
“Why?”
“Because I like orange!”
少しずつレベルを上げて、
“Which do you prefer for dinner—pasta or curry?”
“Hmm… I think curry.”
“Why curry?”
“Because it’s spicy and……”
シンプルな質問でも、このような双方向のやりとりの中で、
子どもは「相手に伝える」「理由を言葉にする」力を、少しずつ自分の中に育てていきます。
「会話って楽しい!」 という気持ちが、アウトプットの原動力になり、
英語で気持ちを伝えることができる楽しさが、思考力と表現力の土台になっていくのです。
3. 英語を使う「遊び」に変える
英語をただの暗記教科にしてしまうと、子どもは次第に興味を失ってしまいます。
けれども、英語が遊びの中で自然に使えるものに変わったとき、学びは一気に深く、自由になります。
講師時代に実際に教室で実施していたミニゲームですが、
- しりとりゲーム(Apple → Elephant → Tiger…)
→語彙の復習も自然にできるアクティビティ。
とっても簡単なので、電車や車での移動時間、場所を問わずに遊べます。 - “Would you rather”クイズ(Would you rather fly or be invisible?)
→選ぶ・理由を述べる力が育ちます。
Yes/Noで答えられないオープン質問は、自分を深く掘り下げて「考える力」を生み出します。
こうした遊びの中では、子どもたちは「正しく言おう」と構えず、のびのびと英語を口にするようになっていくのです。楽しい時間の中でこそ、「伝えたい」という気持ちが芽生え、英語が本当の意味で自分の言葉になっていくのです。
そして何より、親が「話してみる」ことが最大のサポートになる
英語が得意かどうかは関係ありません。
親が勇気を持って英語を話す姿こそが、子どもにとって最大の安心材料になります。
たとえ発音が完璧でなくても、言い回しがたどたどしくても、
大切なのは「伝えたい」という気持ちを、言葉にして届けようとする姿勢です。
その姿を見て、子どもはこう感じます。
「間違えてもいいんだ」
「通じることが大事なんだ」
「英語は「正解」じゃなく、「気持ちを伝える手段」なんだ」
子どもは、大人の完璧さより、挑戦する姿に安心し、影響を受けます。
お母さんが話す一言が、きっとお子さんの「話してみようかな」という気持ちを後押ししてくれるはずです。
最後に
お子さんの英語、今「聞ける力」だけで満足していませんか?
その英語は、本当に「使える言葉」として根づいているでしょうか。
英語をたくさん聞かせることは、もちろん大切ですが、それだけで終わってしまっては、英語は知識のまま。「聞いたことを、自分の言葉として話してみる時間」こそが、英語を自分の力に変えていくカギになるのです。
家庭内は、間違えてもいい、遠慮しなくていい場所。
だからこそ、英語を「使ってみる」挑戦を始めるのに最適な環境です。
聞くだけで止まっていた英語を、伝わる会話へ。
家庭内での英語には、そんな一歩を後押しする力があると思うのです。