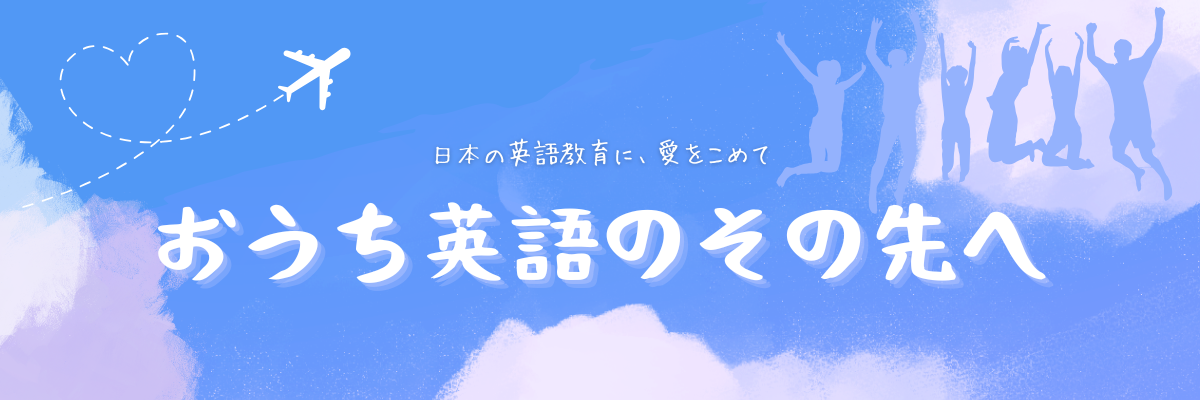こんにちは、桐谷です。
忙しい毎日。つい、子どもの未来のことばかり考えてしまって、 「今、目の前の自分の子と向き合っているはずなのに、心がどこか別の場所にある」 そんな感覚に陥ったことはありませんか?
マインドフルネスとは、
家族の中に、「今この瞬間を味わう習慣」と「心に余白を持つ空気」を育てること。
「〜しながら〜する」ことが当たり前になっている現代。
スマホを見ながらご飯を食べ、明日の予定を考えながら子どもに声をかける。
そんな同時進行の毎日を、ほんの少しだけ立ち止まってみる——それがマインドフルネスの始まりになります。
今回は、そんな「今この瞬間」に優しく目を向ける力、マインドフルネスが、なぜ教育や子育てにおいてとても大切なのかを紐解いていきたいと思います。
マインドフルネスとは?
繰り返しとなりますが、マインドフルネスをもう少しシンプルな言葉にすると、
「今、この瞬間」に意識を向けること
になります。
未来の不安や過去の後悔にとらわれず、今ここで感じていることに静かに気づく。
その心の在り方を大切にする練習です。
起源は仏教の瞑想法にありますが、今ではGoogle、スタンフォード大学、医療機関、そして教育現場にまで広がり、 ストレス軽減や集中力向上、共感力の育成など、科学的にも効果が認められています。
なぜ子育てや教育にマインドフルネスが必要なのか?
子どもと向き合う「余白」が生まれる
子育て中は「〜しなきゃ」が常に頭をよぎりがちです。
でも、その状態では、子どもの小さな変化や感情に気づく余裕がなくなってしまいます。
マインドフルネスは、
親が「今の自分」を見つめる力を取り戻す時間 をくれます。
イライラした時に、反射的に叱るのではなく、 「今、自分は疲れてるな」「この子は助けてほしかったんだな」と気づく。 そ「間」が、親子の関係をまるく変えていきます。
子ども自身の「心のしなやかさ」が育つ
マインドフルネスを親子で取り入れている家庭では、子どもが
- 感情を客観的に見つめられるようになる
- 自分の気持ちを言葉にしやすくなる
- 他者の気持ちに気づく余裕が生まれる
など、自己調整力や共感力が自然と育ちます。
特に思春期や反抗期のような「揺れる時期」には、 この内側の安定が、子ども自身の大きな支えになるのです。
判断を手放し、違いを受け入れる力が育つ
グローバルな社会においては、 「正しさより、違いを尊重できる感性」がとても重要です。
マインドフルネスの習慣は、
「こうあるべき」から「そう感じるんだね」へ
という、柔らかくて深い対話を可能にします。
これはまさに、グローバルマインドセットの土台。
家庭の中でその感性を育てることは、世界へつながる第一歩になるはずです。
家庭でできるマインドフルネスの実践
心を整えることの大切さはわかっていても、
忙しい日々の中ではつい後回しになってしまうもの。
でも、マインドフルネスで大切なのは、日常の中にある「小さな瞬間」に気づくこと。
ここからは、そんな「今ここ」の意識を、
無理なく家庭に取り入れるためのシンプルな実践をご紹介します。
親子でほんの少し、立ち止まってみませんか?
1分間「呼吸」に意識を向ける
「いま、吸ってる」「いま、吐いてる」と、
呼吸を感じてみることからはじめてみるのはいかがでしょうか。
例えば、寝る前、朝の始まりに1分ずつでも十分です。
そこから少しずつ、自分の「感覚」を広げていきましょう。
朝の光、鳥の声、肌に触れる風を一緒に感じながら、
「きれいだね」「風が気持ちいいね」
と言葉にのせていくだけで、子どもの感受性が育っていきます。
ご飯を味わって食べる
テレビやスマホを一旦お休みして、
「今日のごはん、どう?」と親子で話してみることから始めてみましょう。
「どんな味がする?」「温かい?冷たい?」「おいしいね」とシンプルな気持ちを言葉にするだけでも、感覚が「今、ここ」に戻ってきます。
実際に、五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を意識して食べることで、
気が散る思考(過去や未来)から離れられたり、自律神経が落ち着き、副交感神経が優位になる、ストレスレベルが下がるといったマインドフルイーティング(Mindful Eating)の効果は、さまざまな研究で確認されています。
イライラした時は「今の気持ち」を実況してみる
たとえば、イライラしたときに
「ああ、私ちょっと怒ってるな」
「今、すごく焦ってるみたい」
「怒りそうだから、一回深呼吸するね」
と、自分の感情を言葉にして外に出してみましょう。
感情をそのまま否定せず、見つめて言葉にすることで、子どもも自分の気持ちに向き合う力が育ちます。これはマインドフルネスや心理療法の中で「感情のラベリング(affect labeling)」と呼ばれ、近年とても注目されているテクニックです。
これにより、脳の暴走を鎮めたり、自分の感情を客観視できるようになっていきます。
さらにこれを子どもの前で親が実践する、つまり親が「モデル」になって感情を言語化することで、子ども自身も感情を溜め込まずに外に出す力を身につけていくことができるのです。
おすすめの書籍
私自身がたくさんの「気づき」を得て、子育て中に何度も助けられている書籍を3つご紹介します。
特に、長男がまだ生まれて間もないころ、ある講演会を通して出逢った菅原裕子さんの発するメッセージには、その後現在に至るまでかれこれ10年以上救われ続けています。
菅原裕子さんへの感謝と想いは、また別の機会に。
『子どもの心のコーチング』(菅原裕子)
『子どもの心のコーチング』は、子どもとの信頼関係をどう築いていくかを、親の心に寄り添いながら教えてくれる一冊です。読んでいて何度も「そうだったのか」とハッとさせられ、子育てに対する視点が柔軟に、そして深く変わっていく感覚がありました。叱るでも、褒めるでもなく、「信じて見守る」という新しい軸を持たせてくれる、あたたかく力強い本です。
子育て中のすべての大人におすすめしたい一冊。
『スタンフォード大学 マインドフルネス教室』(グレッグ・サーモン)
『スタンフォード大学 マインドフルネス教室』は、感情に振り回されがちな日常の中で、どうすれば自分を整え、他者と心地よく関われるかを、著者のユーモアのある語り口と、科学的根拠をもって教えてくれる一冊です。マインドフルネスを「特別なもの」ではなく、誰にでもできる「心の筋トレ」と紹介してくれていて、実際に“Try it now!”という実践ステップで「呼吸を使った集中法」や「自己共感や他社共感のトレーニング」など、読みながらその場でやってみることができる構成になっています。
『マインドフル・セルフ・コンパッション』(クリストファー・ガーマー)
『マインドフル・セルフ・コンパッション ワークブック』は、自分自身にやさしくなるための、心のトレーニングブックです。感情に寄り添う丁寧な問いかけや実践が豊富で、読むだけで自分を大切にしたくなる気持ちがわいてきます。この本は個人で取り組むための自己実践用ですが、教える側向けの『プラクティスガイド』と対になっています。まず「自分にやさしくあること」の大切さを、深く実感できる一冊です。
最後に:今ここにいる、というギフト
マインドフルネスは「特別な時間」ではありません。
子どもが笑ったその瞬間にちゃんと気づけること、
子どものつまずきに「寄り添える」こと。
そのすべてが、「今ここ」にいる力から始まります。
親が整えば、子どもも整います。
マインドフルネスは、 家族に静かな調和をもたらす空気づくりそのものなのかもしれません。
本記事が、あなたとご家族の毎日に、
やさしいひと呼吸を届けられたら嬉しいです。