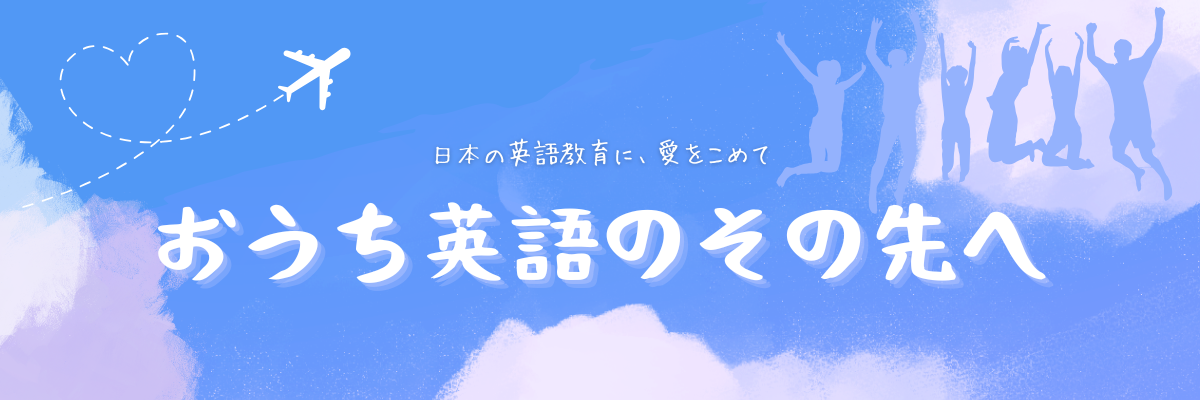こんにちは。桐谷です。
「海外に住んでいれば、自然とグローバルな感覚が身につく」
日本にはそんな信仰(思い込み)が、未だに存在しているようにも感じます。
実際に私が子連れ移住で見たものは、海外で暮らしながらも、異文化理解や対話力を持たないままの子供、大人、そして日本人コミュニティで全てが事足りてしまう便利さ。
一方で、日本にいながらも、日常会話の中で国際的な視点を育み、ニュースを身近な自分ごととして語れるお子さんもいます。
つまり、「どこに住んでいるか」ではなく、
「どう世界を見て、どう考えるか」という視点が、グローバル人材を育てる鍵になると改めて思うのです。
今回は、よくある誤解「海外に住んでいればグローバル人材になれる」という思い込みを、海外で実際に経験したことを例に挙げ、日本国内でも実現できる、本質的なグローバル教育の在り方を、具体例とともにお話したいと思います。
海外在住の方にも、日本にいながらグローバル教育を目指す方にも、有益な記事であることを願います。
海外に住んでいても「グローバルではない」人がいる理由
「海外に住んでいる」ことが、そのまま「グローバルである」ことの証明になる。
そう思っている人は、意外と少なくありません。
けれども、実際には海外で暮らしていても、もったいない程に、視野が狭い方々もいらっしゃいます。
現地の文化に興味を持たず、子どもを日本人コミュニティに置き、買い物や学校で英語に不自由しなくなることで「もう十分」と感じてしまう。
そんな不自由のない環境下で育つと、せっかく海外にいても、英語が話せるようになっても「対話する力」ではなく英語のやりとりで止まってしまう場合が多いのです。
特に親世代では、「英語=生活ツール」で終わってしまい、世界を知り、関わり、対話するという本質的なグローバル教育への意識が止まっているケースも少なくありません。
本当にグローバルな感性とは、環境や言語ではなく、「視点」と「関心」と「問い」の中に育つもの。
だからこそ今、海外に住んでいても「グローバルではない」家庭と、
日本にいながら「世界とつながる子育て」をしている家庭との逆転現象が起きていると思うのです。
英語が話せる人が海外で陥る罠
英語に「困らない」状態で海外に来られた方が、陥りやすい落とし穴があります。
それは、英語がある程度使えるがゆえに、「生活に不自由がないから、それ以上を求めなくなる」という状態です。
買い物も病院も手続きも、英語でなんとかなる。
だからこそ、現地コミュニティとの関わりや文化理解の機会を、自ら閉じてしまうことがあります。
日本でも、外国人居住者との文化の違いが原因でトラブルが生じる場面がニュースで取り上げられますが、海外に住む日本人もまた、現地の文化を理解せずに距離を置いたまま生活することで、同じような見えない壁をつくってしまうことがあるのです。
本当の意味でグローバルな関わりを築くには、英語力だけでは足りません。
現地の文化や背景に興味を持ち、自分自身の視点・関心・教養を育て、英語を通してそれを伝えられること。
そこに初めて、共感や対話、協働の深さが生まれます。
英語で情報をただ伝えるだけでは、人の心は動きません。
心の奥に届く会話は、その人の姿勢や価値観ごと伝わってくるようなことばから生まれるのです。
たとえ発音が完璧でなくても、語彙が多くなくても、
自分の考えや価値観を伝えようとする姿勢がある人は、むしろ信頼と敬意を集めています。
それは、語学力ではなく、「対話する意志そのもの」が人間力として伝わるからです。
子どもたちだけではなく、私たち大人にも問われているのは、
「どんな英語を話せるか」ではなく、
「あなたは何を大切にし、それをどう伝えようとしているのか」
――その根っこの部分なのではないでしょうか。
日本にいながらグローバルな感性を育てる家庭の共通点
Xなどでおうち英語を積極的に取り組んでおられる方々の生の声を聴かせていただいています。
「海外に行かなくても、ここで世界を感じ、考えることはできる」。
そんな視点の広さを日常の中で子どもに伝えているご家庭には、いくつかの共通点がありました。
✅ 1. ニュースや世界の出来事を「家庭の会話」にしている
中東問題、AIと雇用、難民危機、気候変動…。
テレビの向こう側の出来事を、ただ「流れる情報」で終わらせず、「あなたはどう思う?」と親子で語り合う家庭では、子どもが自然に自分の言葉で世界を語る力を育てています。
グローバルな思考力は、日々の家庭の会話から始まっていると思うのです。
✅ 2. 子どもの「なぜ?」に「正解」ではなく「問い返し」で向き合う
「なんで戦争って起こるの?」「どうして貧しい国があるの?」
そんな問いに、すぐに答えを与えるのではなく、
「あなたはどう感じた?」「他の国だったらどうなると思う?」
と問いを重ねる家庭では、対話力と探究心が自然と育ちます。
正解より、思考のプロセスを大切にすることが、グローバルな対話姿勢の土台になるのです。
✅ 3. 英語を暗記教科ではなく、「対話のツール」として使っている
単語や文法の知識よりも、「英語を使って何を話すか」を重視しているご家庭。
たとえば、
- ニュース記事を英語で読んで意見をシェアする
- 今日の出来事を英語で短く話す
といった実用的な場面で英語を育てているご家庭は、子どもにとって英語が「生きた言葉」となっていきます。
英語は学ぶものから使うものへ。グローバルな感性は、その転換から始まります。
✅ 4. 異文化を知識としてでなく、「人」として受け入れる姿勢がある
国や宗教、習慣の違いを「違う=怖い」と感じるのではなく、「違うからこそ知りたい」と受け止める姿勢を、親の行動や言葉を通して伝えている家庭では、子どもも自然に異文化を敬意をもって見つめる力を身につけていきます。
例えば、日本国内であれば、留学生や外国人観光客に興味を持ち、積極的にかかわろうとしているご家庭。海外では、あえて現地コミュニティに入り込み、日本文化を英語で説明するなど積極的に「人」と関わろうとしているかどうかといった体験が、自文化理解×異文化理解という両面からの視野を広げてくれると思うのです。
海外での教育 VS 日本での教育 ― 正解は「どこ」ではなく「どう育てるか」
海外で教育を受けさせれば、子どもは自然とグローバルに育つと、期待を胸に海外に出たご家庭の中には、現地の社会と関わらず、言語の発達も中途半端なまま、「自分は何者なのか」「どこに属しているのか」がわからずに迷子になっている方々も一定数おられるように感じています。
日本にいながらも、日々のニュースや人との対話から世界を自分ごととして捉えようとする家庭の子どもたちが驚くほど深い思考と、自分の意見を語る力を育んでいる中で、
「海外で暮らしさえすれば」
という思い込みのまま判断をしてしまうと、本質的な学びの機会を、自ら手放してしまう可能性があるかもしれません。
教育におけるグローバルとは、「どこに住んでいるか」ではなく、家庭の中でどんな会話が交わされているかで決まるのです。
「なぜそう思う?」「他の国だったらどうだろう?」「その考えを誰に伝えたい?」
そんな問いかけのある日常こそが、国境を越えて対話できる人を育てる土壌になります。
大切なのは、「海外」という場所ではなく、
親子の会話が、どれだけ世界に開かれているか――それが未来をつくる分岐点になると思うのです。
最後に「どこに住むか」より「どんな問いを持つか」
「海外に住めばグローバル人材になれる」――
そんな幻想は、今や過去のものになりつつあります。
本当に大切なのは、子どもが日々どんな疑問を持ち、どんな対話の中で育っているか。
つまり、グローバル教育の軸は地理的な問題ではなく、日常の会話の質なのです。
今、世界に必要なのは、英語が話せる人ではなく、
「心ある言葉」で対話できる人。
あなたの家庭の中で、今日から、その一歩をはじめてみませんか?