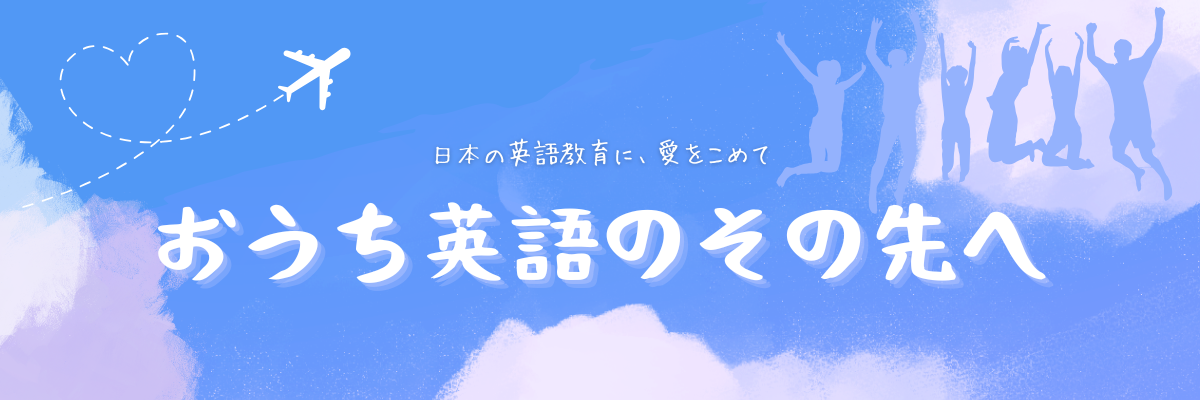こんにちは。桐谷です。
子供の家庭学習をサポートするって、なかなか大変な仕事だと思いませんか?
私が講師をしていた頃、保護者の方からは、成長の過程でぶつかる様々な障害(壁)をいかにして乗り越えるかご相談をいただくことが多かったのですが、中でも、
「子どもが宿題をやらない」
「家庭学習をめぐって親子喧嘩が絶えない」
という、家庭での学習習慣づけに関する悩みはとても多かったと記憶しています。
我が家にも思春期の子供が2人いるので、当時の保護者の皆さまの悩みは実体験としてよく理解できます。
子どもに英語(その他教科も)を楽しく学ばせたい。
でも現実は、声を荒げ、機嫌を損ね、互いに疲弊してしまう…。
おうち英語のその先へ、思春期を迎え、中高生になった我が子とどう向き合っていくのか。
当時の親御さんたちの声を思い出し、そこから見えてきたストレスの少ない家庭学習の進め方を綴ってみようと思います。
なぜ家庭学習はこんなにうまくいかないのか?
児童心理学の観点から見ると、家庭学習がうまくいかない背景には、いくつかの構造的な要因があることが分かっています。
✓ 親が「先生役」を担うと、どうしても感情的になりやすい
✓ 学習そのものに“意味”を感じられていない
✓ 「やらされ感」が強いと、反発が生まれやすい
子どもは家庭を「安全基地」として認識しているので、外では頑張れても、家ではリラックスし、わがままになったり、気を抜いたりするのはとても自然なことです(ボウルビィの愛着理論)。
そして、親が教える立場になると、「感情の距離」が近いため、教育的指導が感情的になりやすいというのもよく知られた現象です。
また、子どもが学習の「意味」や「目的」を理解できないと、内発的動機づけが生まれにくくなり、勉強がただの「やらされること」になりやすいとされています(デシとライアンの自己決定理論)。
つまり、子どもにとって家庭は「安心できる場所」であるがゆえに、 “感情”が先に出やすく、学習モードに切り替わりにくいというジレンマが生まれるのです。
さらに、親が「やらせなければ」「今が大事だから」と焦れば焦るほど、 子どもは“受け身の抵抗”で対抗するようになってしまうのです。
親子喧嘩を引き起こす3つの誤解
上記に挙げた児童心理学の観点から、子どもと親の気持ちがどうすれ違っているのかを考えていきます。
誤解①「子どもはやる気がない」
実際は、やる気がないのではなく、「やり方がわからない」ことが多いのです。
宿題の目的が不明確だったり、量が多すぎたり、やる順番が定まっていなかったり。
我が家にも同じことが起こりましたが、学習の目的を一緒に考え、そのためには今何をすればよいかの逆算でたくさん話し合い、「時間がない」という子供に、学習の優先順位をつけるなど、
私が持っている等身大の知識で(私が実際にどうやって工夫をしているのかを共有)親子のコミュニュケーションの時間を増やすようにすると、子供自身が様々なことを自覚し、結果的にやる気、モチベーションが上がっていったように思います。
これを踏まえて思うのは、子どもに必要なのは、「それをする目的」と「取り組みやすい環境・計画」だと思うのです。
誤解②「やらせることが親の役目」
親が監督者になると、関係がギスギスします。きっと皆さん、心当たりがありますよね?(笑)
けれども大切なのは、「一緒に取り組む仲間」という立場になること。
少しの手伝いや、励ましの声かけで子どもの姿勢は変わります。
我が家の場合は、夕食の後にみんなでリビングに集合して勉強することが多く、
その時間だけは私も、子供たちと「一緒に」を心がけ、読書をしたり資格試験の勉強をしたり、何か新しいことを学ぶ時間にすることを心がけています。
誤解③「怒ればやるようになる」(=怒ってしまう)
短期的には効果があるように見えても、 長期的には「学習=嫌なこと」「親=怖い/うるさい存在」になってしまいがちです。
我が子を思うがゆえになのですが、子供に鬱陶しがられる、逃げられてしまうような親子関係は本末転倒です。私自身、ここは大いに反省があるところですが、怒る(口を出してしまう)前に、“どうすれば楽しくできるか”という視点に立ち戻り、そのためにはどんな声掛けをすべきか、一度深呼吸をし、子供たちに声をかけるようにしています。
家庭学習を「習慣化」するための具体策
習慣化のカギは、以下の3つです。
● 時間と場所を固定する
例えば、毎日「決まった時間」に同じテーブルで取り組むことができる環境を整えること。
これにより「勉強モード」に切り替わる場をつくることができます。
家族で話し合い決めても良いですし、自然とそのパターンが習慣化されるように働きかけても良いかと思います。
● 10分だけでもOK。「短く、続ける」
高すぎるハードルはチャレンジする前に気持ちが萎縮してしまいます。
最初から30分、1時間を目指さないで、5分でも10分でも、「できた!」という体験を積み重ねることを優先することが大切です。
● 見える化する(チェック表・シールなど)
中学生、高校生になっても、意外とこの「見える化」は効果があると思います。
視覚的に進捗がわかる仕組みを取り入れることで、小さな達成感を日々味わえるようになるからです。
現場で実践していた3つのアプローチ
英会話講師として働いていた頃、私は家庭学習に悩む親御さんに、次のような方法を提案してきました。
①「学習をゲーム化」する
例えば、英単語をカードにしてカルタで覚えることや、タイマーを使って「○分チャレンジ」。
今日の課題を「くじ引き」でランダムに作るなど、遊びのエッセンスを加えてみてくださいということです。
これは、男の子を中心に一定の効果があったと体感しています。
②「親子で一緒に取り組む時間を設ける」
宿題を「やらせる」のではなく、「一緒にやる」
また、子供が先生役になって親に教えるなど、なんでも「教えて」というスタンスで子供に主導権を渡すスタイルです。親に頼られた子供は嬉しく、お母さんを助けるために張り切ってくれるお子さんも多いのではないかと思います。
③「宿題の目的を明確にする」
特に高学年、中高生は、なぜそれをやるのか、親子で共有することが大切です。
英語に関しても「覚えること」ではなく「使えるようになること」に焦点を当て、さらに、英語を使えるようになると「どんな未来が待っているのか」何気ない会話の中で子供に伝えていくことは大切だと思っています。
親も子も「楽になる」家庭学習のヒント
家庭学習において、最も大切なのは、完璧にやらせることではなく、「毎日ちょっとずつ、続けること」です。
- 子どもができたことに「気づいて」あげる
- 「昨日より一歩前進したね」と声をかける
- 週末は「休む日」にして、心のバランスを取る
難しく考えず、お母さん自身に置き換えてみてください。
小さな成功体験は、やがて「学習する自分」を育てていきます。
「学習の成果」よりも「関係性の質」に目を向けていくことが子どものモチベーションを高めます。
そんな関係性の中で、子供は成長をしていくのです。
最後に──家庭学習は「場づくり」から始まる
宿題や勉強をめぐって、大喧嘩になってしまった時。
やる気のなさに、親としてむなしくなり、がっかりした時。
多くの保護者の皆さまが経験していることかと思いますが、でも思い出してほしいのです。
もともとは、 「何かが突出してできる子」よりも、「学びを楽しめる子」に育てたかったのではありませんか?
その第一歩は、怒ることでも、やらせることでもなく
「やってよかった」と子どもが思える、小さな学習の場を整えることから。