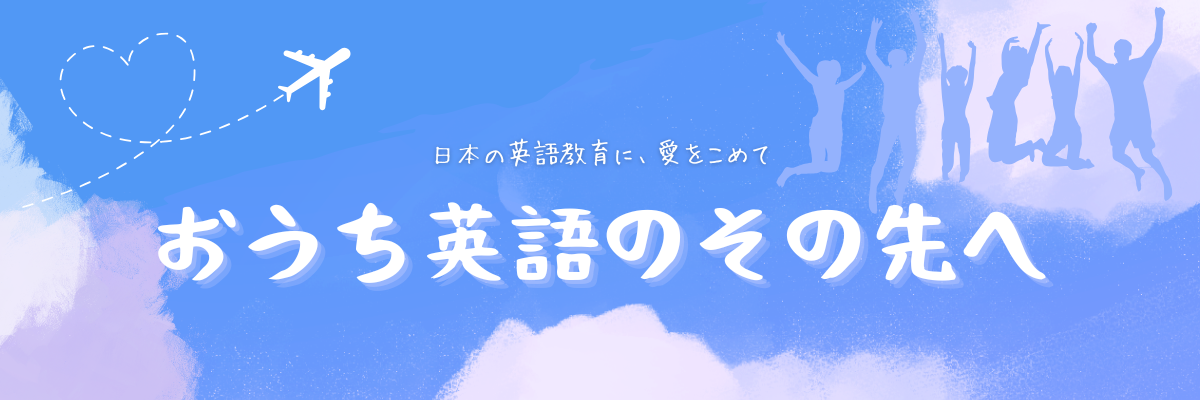こんにちは。桐谷です。
最近、こんな風に感じたことはありませんか?
「おうち英語、いつまで続ければいいんだろう」
「頑張ってるけど、本当に意味があるのかな」
「このやり方、うちの子に合ってるのかな…」
子どものためを思って始めたおうち英語。
けれども、続けるほどに、「これでいいの?」という不安や、
「正解が見えない」もどかしさに、心が揺れることもあるかもしれません。
でも、そんなふうに立ち止まって考えているのは、
すでに、ただやらせるのではなく、「本当に意味のあることをしてあげたい」と願っている証だと思うのです。
今日は、「終わりのないおうち英語、どこまで頑張るべき?」という疑問を、
一緒に考えてみたいと思います。
「頑張る」って、誰のため?おうち英語に潜む「がんばり信仰」
おうち英語の世界には、努力を美徳とする空気があるように感じます。
「毎日英語の絵本30冊!」
「1000時間のインプット達成!」
「ネイティブレベルを目指して!」
もちろん、努力は素晴らしいことですが、
その「がんばり」に、一度疑問を持って考えてみたいのです。
その努力は、今の子どもにとって本当に必要なものですか?
それとも、「頑張っている自分」でいようとする、大人の安心感のためではありませんか?
おうち英語は、競争でもなければ、見えない誰かと比べるものでもありません。
一番大切なのは、子どもが安心して、自分のペースで言葉と向き合える環境であること。
どんなに正しいように見える方法でも、
「やらなきゃ」「続けなきゃ」と義務のようになったとき、
子どもの心には、小さくても確かな「重さ」が積み重なっていきます。
親の努力が「愛」ではなく「焦り」からくるものであったなら、
その空気は、気づかぬうちに子どもに伝わってしまうと思うのです。
正解のない道で見失いやすいもの
おうち英語には、明確なゴールや合格ラインのようなものがありません。。
「どこまで続ければいい?」
「何をもって成功と言えるの?」
「話せるようになったら、それで終わり?」
そんな問いに、誰もが納得するような答えを出すことはできません。
だからこそ、私たちは時に、目に見える成果やスキルに頼りたくなるのかもしれません。
でも、ひとつだけ確かなことがあります。
それは、
英語は「育児の手段」であって、「目的」ではないということ。
どれだけ発音が良くても、語彙が豊富でも、
もし子どもが自分の考えを持たず、他人との対話を避けるようになってしまったら、
それは「英語ができる」とは、少し違う話になってきます。
本当に育てたいのは、ことばの裏にある心や姿勢。
英語は、それを育てるための道具であり、きっかけにすぎないのです。
親の不安に寄り添う3つの問い
おうち英語に迷いや不安を感じたとき、
誰かの正解を探すよりも、まずは自分自身で考えてみることが大切です。
①「うちの子に合った学び方だろうか?」
誰かの成功体験は、ヒントにはなっても、答えではありません。
動画の音に引き込まれる子もいれば、静かに絵本の世界に浸る子もいます。
毎日コツコツ続けるのが得意な子もいれば、気分に波がある、感覚派の子もいます。
あなたのお子さんは、どんな学び方の癖を持っているでしょうか?
そのリズムや個性に、ちゃんと目を向けていますか?
英語の力もまた、子どもの個性を尊重するところから育ち始めます。
②「私自身、英語とどう向き合っているだろう?」
「英語が苦手な私が、子供に教えていいのでしょうか?」
「発音に自信がないから、カタカナ英語の私が話しかけてもいいのでしょうか…」
教育現場で保護者様のそんな声を、たくさん聞いてきました。
けれども、本当に必要なのは、完璧な発音でも、流暢な会話でもありません。
大切なのは、「間違えてもいいから伝えてみよう」とする姿勢。
そして、挑戦する背中を見せることです。
あなたは今、英語を楽しめていますか?
それとも「ちゃんとやらなきゃ」と、自分を責めていませんか?
子どもは、言葉そのものよりも、言葉と向き合うあなたの姿勢をしっかり見ているのです。
③「英語を通して、どんな力を育てたい?」
目指したいのは、英語が話せる子でしょうか?
それとも、英語を通して、自分の思いを世界に届けられる子でしょうか?
その答えは、ご家庭ごとに異なっていて当然です。
でも、一つだけ言えるのは、
これからの時代に必要なのは、英語力そのものではなく、言葉の奥にある「伝える力」と「聴く力」だということ。
子どもが自分の声で話し、誰かの声に耳を澄ませる。
そんな力を、英語という道具を通して育んでいくことこそが、
おうち英語の本当の価値なのかもしれません。
実際に「続けた先」にあるもの
ここでひとつ、私が移住先で出会った日本人ご家族のお話をご紹介します。
そのご家庭では、お子さんがまだ幼い頃から、英語の絵本や音声教材を暮らしの中にごく自然に取り入れていました。
毎日決められたノルマがあったわけではなく、「楽しめる範囲で、続けられるペースで」を大切にしていたそうです。
けれども、小学校の中学年ごろ、こんな悩みが現れてきました。
「英語は好き。でも、話すのがなんだか恥ずかしい」
「聞き取れるけど、自分の言葉が出てこない」
そのとき、お母さんが意識を向けたのは、英語を伸ばすことではなく、「気づかせること」でした。
「今日は、自分から“Hello”って言えたね」
「“I like it”って気持ちをちゃんと伝えられたの、すごくいいね」
子どもの中の小さな「できた」を見つけて、言葉にしてあげる。
その一言が、子どもの中に「伝えられた」「通じた」という実感を積み重ねていったのです。
やがてその子は、「もっと自分の言葉で発信できる場所で学びたい」と自ら希望し、海外移住を決意。
今では中学生となり、現地校で英語も日本語も使いこなしながら、自分の気持ちを堂々と語れる子に育っています。
「英語が話せるようになったことより、
自分の思いを言葉にできるようになったことが、何よりの成長です。」
と、お母様が仰っていました。
おうち英語は、短期的な成果を測るものではありません。
言葉を通して「自己表現の力」を育てていくプロセス、それこそが、続けた先に見えてくる本当の実りなのだと、改めて感じさせてくれました。
最後に──手放すことは、あきらめることじゃない
おうち英語を続けるなかで、
ふと立ち止まり、「このままでいいのかな」と感じる瞬間があります。
でもその問いは、決して「やめたい」という気持ちではなく、
「もっと本質的な意味を求めている」という、あなた自身の成長のサインかもしれません。
頑張りすぎた日があれば、立ち止まって深呼吸してもいい。
不安に揺れたときは、はじめに込めた「わが子への想い」を、もう一度見つめてみてください。
大切なのは、英語ができることよりも、
英語という「言葉の体験」を通して、自分の子供とどう向き合っていくか。
そこにこそ、親としてのまなざしが、
そして、おうち英語の本当の価値が宿っているのではないでしょうか。