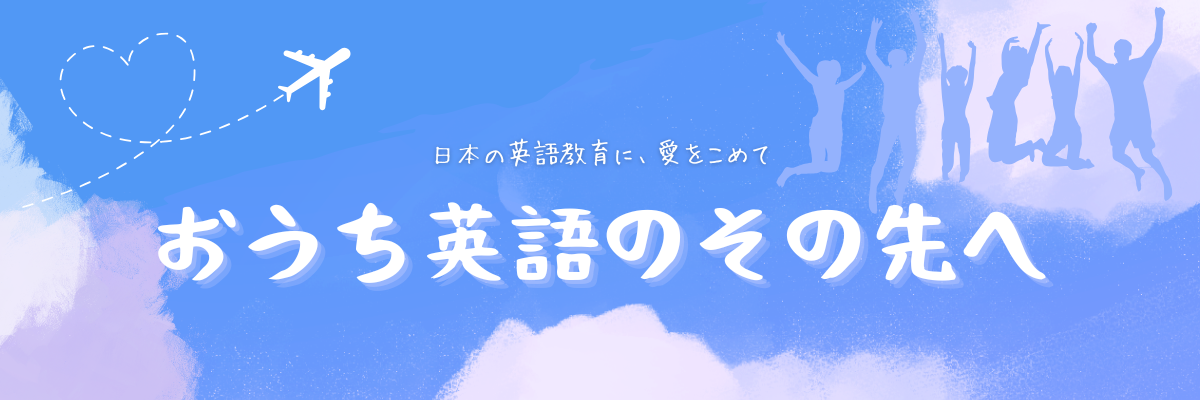こんにちは。桐谷です。
今日のテーマは、もしかすると少しだけ胸に刺さることがあるかもしれません。
でも、それだけ大切で、目をそらせない問いだと思うのです。
「日本の英語教育って、もしかしてぬるすぎるのでは?」
そんな違和感を、感じたことはありませんか?
もしあるとしたら、それは、親として未来を見据えるあなたの直感が働いているのかもしれません。
今回は、日本と世界の英語教育を比べながら、
今、私たちが子どもに伝えたい本当の英語力とは何かを、
一緒に考えていきたいと思います。
世界では、英語は生きるための必須スキル
今、世界の多くの国では、英語は単なる「教科」ではなく、生き抜くための道具です。
グローバルな就職市場、海外大学、ITスキル、AI──
英語はあらゆる場面で「入口」として求められるスキルとなっています。
たとえば:
- 小学校から英語でディスカッションをする国(例:インド、フィリピン)
- 教科書が英語オンリーの国(例:マレーシア、南アフリカ)
- 学校外でも英語メディアやSNSを使いこなす子どもたち
こうした国々の子どもたちは、自然と「世界の文脈」で英語を学んでいるのです。
日本では、なぜここまで「ぬるい」のか?
日本でも、小学校から英語の授業が始まり、英検や英会話も盛んになってきました。
それ自体は素晴らしいことです。
でも──
その「英語」は、本当に世界基準でしょうか?
多くの学校では、未だに
- 文法や単語の暗記が中心
- 英語で自分の意見を言う機会がほとんどない
- 英語の授業は週に1回だけ、しかも日本語中心
こうした環境では、「英語を学んでいるつもり」で終わってしまう危険があります。
これは決して、先生や学校を責めたいのではありません。
構造的に、「本気で使える英語を育てる設計」がまだ整っていないのです。
ゆるい英語教育に慣れすぎた日本の私たち
英語力を底上げする為に、もっと本気で学ばなければならないのに、
どこかで「まあ、これくらいでいいか」と感じてしまう──
私たち親自身も、実はこの「ゆるさ」の文化の中で育ってきた世代なのかもしれません。
「自分も英語は苦手だったけれど…」
「日本にいる限り、そこまで必要ないかも?」
「楽しくやってくれたらいいかな」
そのやさしさはとても尊いものだけれど、
その奥にある備えのゆるさが、未来の選択肢を静かに狭めてしまうこともあると思うのです。
今、家庭から変えられる3つの視点
学校の制度を変えることは、簡単ではありません。
でも、家庭の中で育てられる学びの姿勢や英語との向き合い方には、大きな可能性があります。
「英語で何を学ぶか」に目を向ける
英単語や文法ばかりに目を奪われるのではなく、
英語を通してどんな思考力・表現力を育てたいのか。
その視点に立ったとき、英語は単なる科目から、「学びのツール」へと変わります。
英語に「汗をかく経験」を与える
ゲームのように楽しい英語も良いけれど、
伝わらない悔しさや、言い直して伝えようとする工夫――
そうしたもどかしさもまた、言葉を育てる大切な時間です。
親自身も「学び直す姿」を見せる
子どもは、親の言葉よりも親の背中をよく見ています。
たとえ流暢でなくても、「間違えながらでも挑戦する姿勢」は、
子どもにとって何よりのメッセージになります。
最後に──ゆるさを責めず、でも見て見ぬふりはしないで
日本の英語教育は、たしかにゆるいかもしれません。
でも、そのゆるさを責める必要はありません。
大切なのは、そこに気づいた私たちが、どう行動するかです。
子どもたちはこれから、世界とつながり、働き、生きていきます。
その未来に、「本気で通用する英語力」を手渡してあげたい。
その第一歩は、「現実を見る勇気」と「学び直す愛」から始まりまるのです。